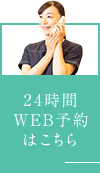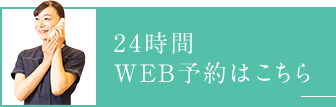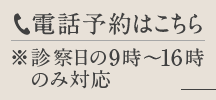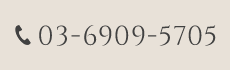新年明けましておめでとうございます!
2025年が始まりました!
皆さんはどのような年末年始を過ごされましたか?
当院は皆さんの健康の助けになれるよう精進していきます!
また、昨年から外来、内視鏡検査の他、栄養指導も行ってきました。
今年は食事面のサポートもできるよう栄養指導もたくさん取り組んでいけたらと思います。
さて、お正月が過ぎ、1月7日は「人日(じんじつ)の節句」、または「七草の節句」があります。七草がゆを食べる日ですね。
さっそくですが七草すべて答えられますか?
答えは、、、
・セリ
・ナズナ
・ゴギョウ
・ハコベラ
・ホトケノザ
・スズナ
・スズシロ
すべて答えられましたか?
すべて覚えていらっしゃった方は素晴らしいです!
これは春の七草と呼ばれ、それぞれに意味や効能があります。
<芹(セリ)>
芹には、「新芽がたくさん競り合って育つ」という様子から、勝負に「競り」勝つという意味合いが込められています。胃を丈夫にする効果や解熱効果、利尿作用、整腸作用、食欲増進、血圧降下作用などの効果があるといわれています。
<薺(ナズナ)>
薺(ナズナ)とは、現代でいう「ぺんぺん草」のことです。薺には「撫でることで汚れを取り除く」という意味が込められています。解毒作用や利尿作用、止血作用、腎障害やむくみに効果があるといわれています。
<御形(ゴギョウ)>
御形(ゴギョウ)とは、現代でいう「母子草(ハハコグサ)」のことです。これには仏の体という意味合いが込められています。咳や痰、のどの痛みに対して効果があるといわれています。
<繁縷(ハコベラ)>
繫縷(ハコベラ)は、「ハコベ」とも呼ばれています。これには、「繁栄がはびこる」という意味合いが込められています。また、昔から腹痛薬として使用されており、胃炎や歯槽膿漏に効果があるといわれています。
<仏の座(ホトケノザ)>
仏の座(ホトケノザ)は、小鬼田平子(こおにたびらこ)とも呼ばれています。葉が地を這うように伸び、中心から伸びた茎に黄色い花をつけます。これには、仏の安座という意味合いが込められていますが、胃の健康を促し、歯痛や食欲増進などの効果があるといわれています。
<菘(スズナ)>
菘(スズナ)とは、現代でいう蕪(カブ)のことです。これには、神を呼ぶ鈴という意味合いが込められています。菘は、胃腸を整え消化を促進し、しもやけ、そばかすにも効果があるといわれています。
<蘿蔔(スズシロ)>
蘿蔔(スズシロ)は、現代でいう大根のことです。これには、「汚れのない清白」という意味合いが込められています。美容や風邪に効果があるといわれています。
このように個々に由来や意味が込められています。私たちは1月7日の「人日の節句」にこれらの春の七草と呼ばれる7種類の草を入れた七草がゆをいただき、無病息災、長寿健康を願う日本の伝統です。
皆さんお気づきだと思いますが、胃腸に効果がある野菜や野草が多くみられますね。お正月のごちそうで疲れた胃腸をいたわるためという説もあります。
現代ではこのすべての野菜、野草を集めるのは一苦労かもしれません。スーパーなどには便利な七草がゆの素が売っていたりしますのでぜひ活用して日本の文化を味わってみてはいかがでしょうか?
当院では高血圧、糖尿病、脂質異常症だけでなく胃腸の疾患に対する栄養指導を行っています。また必要時には医師の診察後に胃カメラ・大腸カメラの検査などを行うこともできますので、お気軽にご相談ください。